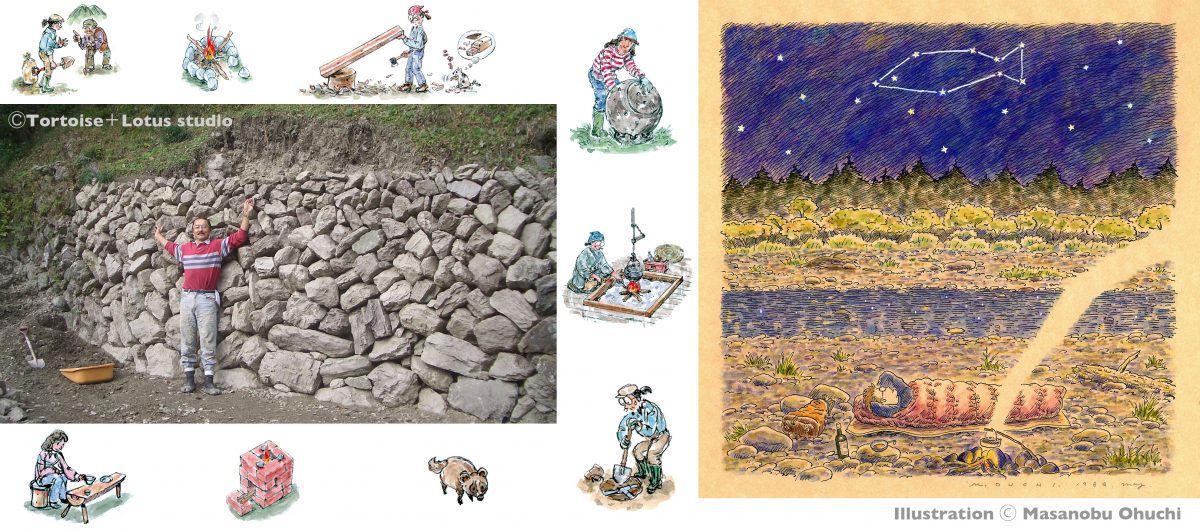新年の一回目ということで群馬での「床の間」の思い出を書いてみる。
前に書いたように、住宅事務所の和室に床の間をつくるのだが、その納まりを考えているうちに、いまから8年前、群馬の高崎にある蔵のギャラリー「棗(なつめ)」で個展と新作紙芝居のライブをやったことを懐かしく思い出している。
棗は明治初期の高崎商家で、いわゆる座敷蔵である。この蔵は区画整理で壊される運命にあったのだが、所有者の平野さんが蔵をどうしても残したいと100トンもの重量のある建物を曳家で動かし、日本茶喫茶・ギャラリーとして再生された。




棗は1階2階それぞれに床の間を持っていて、どちらもすばらしいものであった。床はケヤキの1枚板であるが、割れやそり、すき間がほとんど見られない。そして1階には黒柿が使われ、2階には鉄刀木(タガヤサン)が使われている。特に1階の落としがけには稀少な黒柿の中でも滅多に出ないという孔雀杢(くじゃくもく)が使われていた。



こんな床の間に似合う絵なんてあるはずがないのであって、ここはどうしても掛け軸が必用ということになり、そこで私が神流川流域にちなむ古典文学から文章を抜粋し、yuiさんが和紙に書を書き、みずから表装するということになったのである。
最初は圧倒されるような棗の建物だったが、展示を終えてしばらくするうちに調和の音が感じられるようになった。この空間が私たちの作品を受け入れてくれたのだ、と思った。


この個展では自然素材の素晴らしさというものをあらためて感じさせてもらったし、展示というものはその空間性とコンセプトが何よりも重要なのだということを再認識させられた。「何を飾るか」は重要だが、和空間では「何を飾らないか」ということが、さらに重要なのだ。

住宅兼事務所の完成まであとひと月半。いい床の間を作り、暮らしの中でその空間を楽しみたいと思っている。