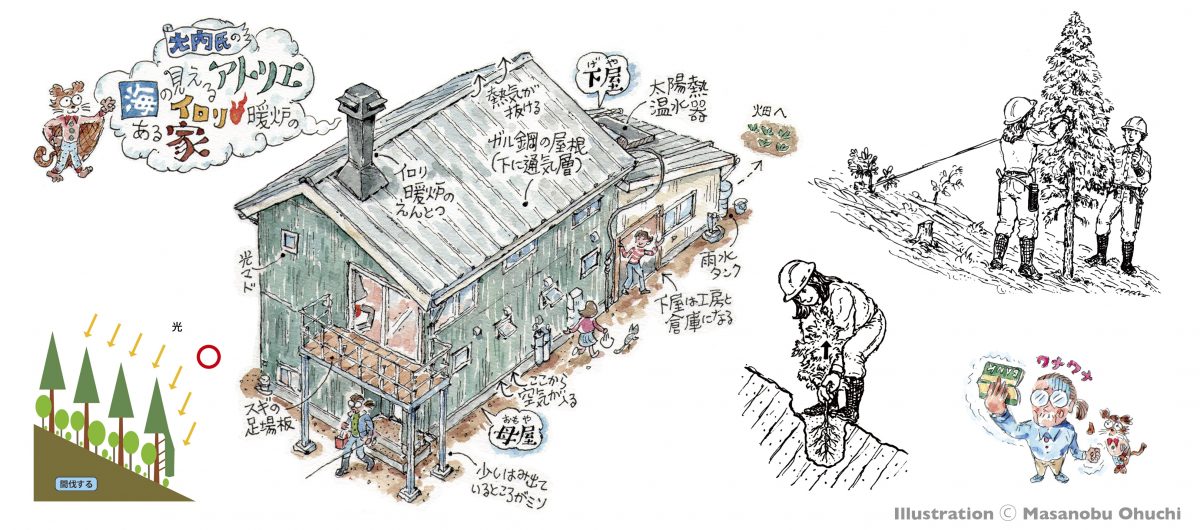以前、河原でキャンプしたとき、東京から来た客人が「焚き火で何でもできるんですねぇ」と感心していた。それを、私は家の中でもやっているわけだ。
火鉢を見ると思い出すのは母方の祖父の家で育てられたときの記憶である。カマドや火鉢を使っていた最後の時代に私は遭遇することができた。

祖父は食パンを大事そうに火鉢でこんがり焼き、バターの銀紙をはいで焼き目の余熱で上手に塗るのだった。また、近くの高校の庭にあるイチョウの銀杏を拾ってきては、火鉢で焼いて食べていた。
叔母たちはそんなことが「貧乏臭くて嫌だった」と述懐するのだが、私はそんなことが大好きな少年だった。

その裸火が消える瞬間を多感な青春期に味わうことになった。私はそんな時代から逃げ出すように、実家を脱出して東北の大学へ行き、みちのくの山で釣り三昧の日々を送った。
当時は山に入ればたいてい未舗装で、今様な高性能な4輪駆動車があるわけではなく、 それゆえ奥地に行けば美しい野生の溪魚が釣れた。その獲物 を河原の流木で焼いて食べたのである。思えば自由な焚き火が許される最後の時代であった。(拙著『囲炉裏と薪火暮らしの本』)
北海道産の金時豆を、群馬時代のストック豆と同じ時間をかけて圧力鍋で炊いたら柔らか過ぎてドロドロになってしまった。

9時半を過ぎると2階の食堂に陽が差して温かくなる。ちゃぶ台を改造してつくった丸テーブでコーヒーを飲む。

2階のピクチャーウィンドウから見える雑木林がようやく色づいてきた。四国なんだな。