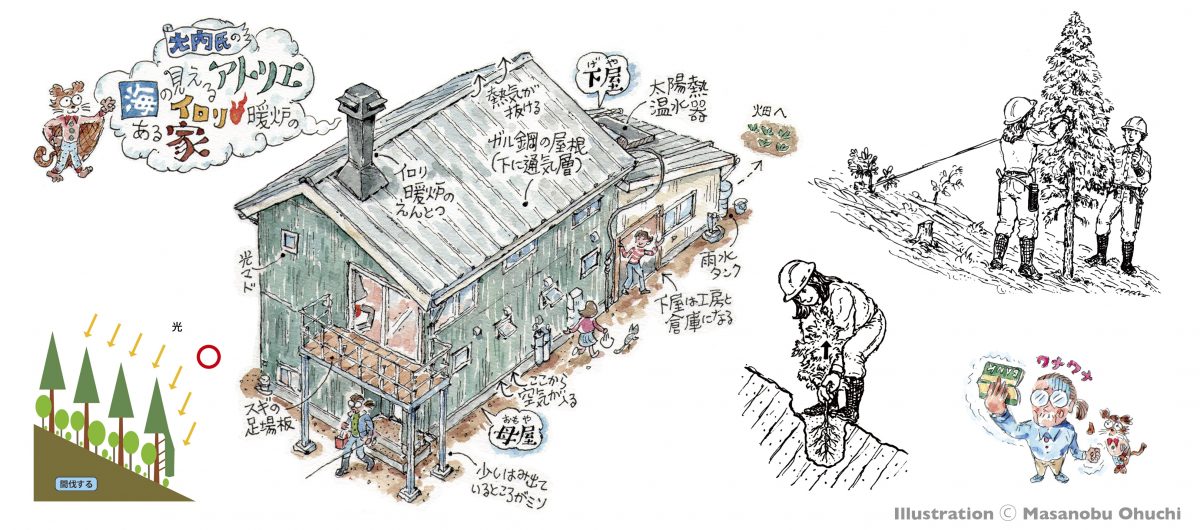昨日、トチカンで木を引き出していた。一昨年の秋に伐っておいたスギだが、つまり林内に1年半以上放置してあった木なのだが、腐りはみられない。秋伐りの木は虫食いや腐食に強いというが、驚くべきことだ。春・夏伐りの木は林内でぼろぼろに朽ち始めているのだから。
そのスギ林の内部である。ずいぶん枝を拾いまくっているが、ちょいと足をのばせばまだまだ枝が拾える。間伐前のスギ林は、およそ全国すべてこのような状態になっており、その枝葉を使う人はほとんどいない。膨大な燃料資源は土に還ろうとしている。

その長いのを集めて白いんげんの支柱に追加する。この支柱、雨ざらしで放置しても3年くらいは保つ。集落の人たちは割り竹を使うようだが、アトリエ敷地には残念ながら竹林がないのだ。

さて、そのスギ林の土に気になる場所があった。土が地面から吹き出しているような箇所がいくつかあり、その土が粘土のようなのだ。団子をつくるとよく粘ってまとまる。

土団子のサンプルをイタルさんに見せると「うん、そりゃ粘土だよ。もっと青いのもあるが」との返事。やったぜ。粘土採集はずっと頭にあっていつも気にかけていたのだが、なんと鉱脈はすぐ近くにあったのだ。
さっそくバケツ1杯分を採りにいく。これにイネ藁を混ぜ込むと土壁ができる。また土器も焼くことができるはずだ。そうだずっと気にかけていた囲炉裏で焼く「縄文陶芸」をさっそくやってみよう。

粘土の中に入っている有機物や小石を取り除き、棒で押さえながら、採りきれない小石をつぶしていく。三波石の小石が混ざっているのでやや青い色が入っている。

水を少し混ぜるとよく粘る。テストピースもつくらずいきなり手びねりでぐい飲みをつくってみる。陶芸家吉田明氏の本(『いつでもどこでも 室内縄文陶芸』)によれば、砂を混ぜると割れにくいと書いてあるが、小石の砕けたものがかなり含まれているのでこのままでいく。

灰をまぶして一気に乾燥させる。ここが「縄文陶芸」の画期的なところだ。灰を吸ったとたん、粘土のふにゃふにゃ感がなくなる。

湿った灰は指でひっかいて新しい灰をつけていくとどんどん乾く。もうコチンコチンになっている。

囲炉裏に火を入れて、じわじわ火に近づけていく。整形から1時間くらいで灰が落ちるくらい乾いている。


火に近づける。

内側もかなり乾いてきたのを確認して、いよいよ囲炉裏の灰の中心へ埋め込み、その上で火を焚く。

ちょうど1時間で取り出してみた。ものすごく熱いので慎重に。

冷ましてから(冷えるまでかなり時間がかかる)灰を洗ってみたら土がまだ焼けていなかった。

そこで、朝まで熾火の灰に埋めておいたら、焼けていた。色がテラコッタ、埴輪の色になっている。右は洗ったときの色。焼けているか否かは叩いてキンキンという金属音に近い音がするのでわかる。

濡らした水が乾いてきた。

砂石が混じっているのが見える。砂が多いほうが焼成のとき割れにくいそうだ。しかし砂が混じると粘性がなくなって土器のかたちはつくりにくい。ところが縄文土器には限界以上に砂が混じっているものが多いそうで、吉田さんは「植物性の糊や動物のゼラチンなどを混ぜていたのではないか」と推理している。

灰を使って乾燥を極端に早め、囲炉裏の灰の中で熾炭で焼くという画期的な方法は、縄文人の生活スタイルにぴったりで、まったく無理がない。縄文土器鍋で煮物やカレーや米も炊け、それは非常に美味しいという。また、蓋つきに鍋をつくれば、火に強いので空焚きしてオーブンのように使うこともできる。

ともあれ粘土の発見は大きい。じつはイタルさんに粘土の場所を訊こうかとも思っていたのだが、それはキノコのありかと同じで人に聞くべきことではなく、簡単に教えるものではないのだ。自分で発見できるまで、じっと待っていてよかったかもしれない。
この粘土で古民家再生の「土壁」、実用品としての「縄文土器」、「石窯」などをつくることができそうだ。これでまたアトリエのスタイルが大きく前進するだろう。

追記:縄文陶芸の吉田明さんは、日の出町時代に家の近所にアトリエがあり、娘と共に交流した思い出があります。その後、工房を新潟の十日町に移され、新天地でご活躍のただ中、残念ながら60歳という若さで亡くなられました。
(本記事は旧ブログ「日の出日記(3)」開始記事となります)