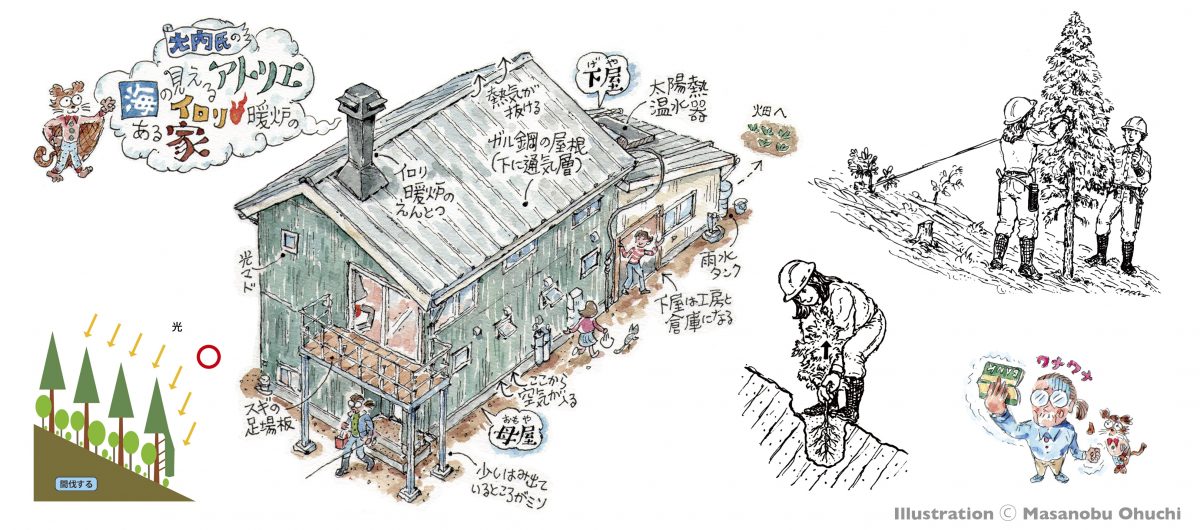3日目の朝。落伍者なし(笑)みんなバリバリに元気です♬ 朝のセルフサービスご飯。納豆が大人気で足りなくなった模様(笑)。

昨日こなしていなかった薪火に関するメニュー、クサビによる丸太割り。そこから厚板採りのハツリもやってみせる。

思いのほか皆が熱心に取り組んだのはは竹工作だった。子供たちだけでなく大人たちもハマってしまうようである。僕が竹のスクレーパー(おろし筅/せん)を作って見せたら「私もつくりたいっ!」と挑戦するお母さん出現。最後のささら割りが難易度高いのです。

今日のメーンイベントは生きた鶏の解体である。

近くで飼っているという地鶏を2羽。首を切って湯につけて羽をむしる。ここまでの作業、案外早くて簡単そうだったが、子供たちは真剣なまなざし。事前に「見たくない人は部屋の中で待機するように」と通達。

エサにこだわっているという鶏なので当然ながらガラからはよいスープがとれる。焚き火で吊り鍋で炊くことに。

胸肉とささみはさっと湯通ししてたたきに。これは絶品だった。

もも肉は炭火で皮からじっくり焼く。これまた絶品❗️ このあと、レバー・ハツ・砂肝など内臓系も塩焼きに。

親鳥の肉は硬いので、あらかじめミンチにして山芋をまぜたハンバーグも提供。そして美味しいお米のおにぎり。

もうひとつ焼き網が延長されて、野菜も焼かれるバーベキューに。三又の焚き火に炭を放り込んでおき、炭がおきたところで隣の焼き網の下に追加する。地面に石とレンガがあれば、専用のグリルがなくてもできる。

焚き火の中にはアルミホイルに包まれたジャガイモが。焚き火、使いこなすと本当に便利です。しかも薪火はそれだけで料理をおいしくします。

さすがに連続して焚き火の熱気にあたって限界がきてしまい、氷水を飲みながら部屋に逃げ込んでいたら、Sくんたちが「じゃがバターできたよ!」と部屋まで持ってきてくれた❣️

今回、主催者「シューレのたね」のNさんが、夜の焚き火を囲んで詩の朗読をしてくれる予定だったのだが諸事情で欠席。こういうイベントでは「音」の記憶も大切な要素だと思うので、雨天のときのために持ってきたタマリン紙芝居を最後に演じて締めることにした。

泳ぎに行った小渓流の両わきがスギの人工林だったから、ちょうど良かったかも? 次回やるときは綾部付近の流域図(川と山と都市部の関係がわかるイラストマップ)があるとよいかなと思った。
今回は新聞とラジオの取材が入り、お母さん方が著書をずいぶん購入してくださった。11月にはつむぎの杜の裏庭に縄文小屋をつくるイベントを計画しており、すでに予約がどんどん入っている模様💦
というわけで、大きなケガもなく、縄文サマースクールは無事終了。参加者の皆さん、スタッフの皆様、ありがとうございました❣️