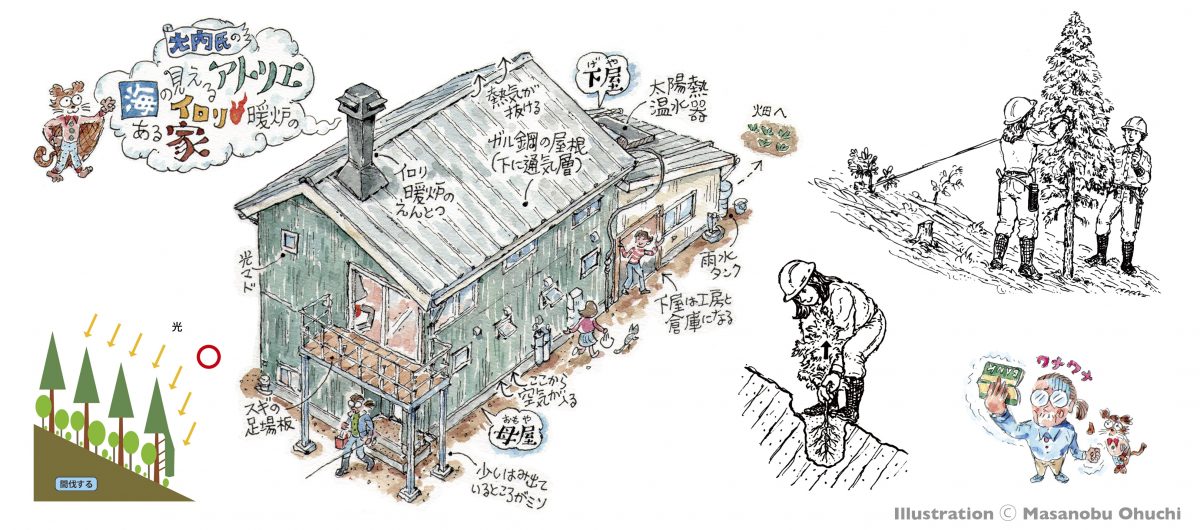瀬戸内海・豊島での「大地の再生」1泊2日のワークショップへ。高松から豊島へは高速船が運航しており、家浦港まで約35分と近い。が、車は乗り入れできないので手荷物満載で船に乗る。背中のリュックには宿泊とナタ・ノコ・カマがセットされた「大地の再生」腰袋。そして両手には講演用のパソコンと煮炊き用の羽釜。下見は先々月にしており、センスいいチラシも作っていただき、島の地元の人たちを中心に集客もできたもよう。

講義は「神愛館」の一部ゲストハウス施設の中で行った。プロジェクターを用意していただき、午前中いっぱいというみっちりの座学だったが、島に初めて「大地の再生」が入るということもあり(前の週に島内で映画「杜人」が上映されていた)みな熱心に聞いてくれた。
地図の赤丸が神愛館の位置であり、地図でみると谷の流れと風みちを塞ぐように鉄筋コンクリートの建物が立っている。下見では海の出口にも周ってみたのだが、やはり泥が堆積して出口(青矢印)が詰まっている。

昼食をいただいて・・・(素敵なオーガニックプレートという感じで美味しかったです音符)、

午後からさっそく海の出口に周ってみる。海岸には歩いて程よい距離。途中に休耕地とため池が見え、長年放置されたため周囲はヤブ状の密林になっている。

沢の出口はこんな感じでゴミが散らばる。森と砂浜との境界線、ビフォー。

砂浜で伏流して水みちは海までつながっていない。

小雨混じりの寒い天気だったが、参加者全員でゴミ拾いから始めて、海までの溝を掘ってもらった。

上流側も、泥と障害物を取り去っていく。

もうどれくらい放置されたままだったのだろう? 大量のゴミと厚く堆積したヘドロ・・・だが、これが片付いて泥の中に清流が流れ始めるのをみるとき、参加者の目が輝く。

格闘することおよそ1時間。

海へ泥水が流れ始める。

上流側に進んだチームも気持ち的にひとくぎりがついた様子。

森と砂浜との境界線、アフター。泥が流れると透明な水が上流からゆっくりと回ってくる。沢筋上部のヤブを払って風みちを通しておくことも重要だ。次の大雨が来たとき、表面に出た大量の泥が流され、沢筋が大きく開いていく。

けっこうな型のモクズガニが出てきた。このヘドロの中でもたくましく生きている。強烈なメッセージを感じた。

神愛館に戻って施設前の風の草刈り。

ここは野外での調理にちょうど良い広場だった。隣の斜面には竹も石もあって三又囲炉裏の材料に困らない。

今回は三又囲炉裏づくりと薪火体験、そしてスパイスカレーづくりもワークショップのメニューに入れてあった。講師の僕は三又囲炉裏づくりを実演指導しながら、調理場に回って野菜の切りをお願いするなどフル回転で超・忙しい💦

いつも思うのだが、三又囲炉裏で煮炊きをするとき「薪を持って来てください」と現地の人や参加者に頼むと、たいがい薪ストーブで使うような太い広葉樹の高級薪を探して持ってくる。しかし、煮炊きには枯れ枝や小枝のような細い薪のほうが向いているのであり、火力も強いし火のコントロールもしやすいのだ。

なんとか時間通りにカレーも完成して好評を得てホッとする。

参加者に神戸のMさんがいらしていて、男木島の石積み以来6年ぶりの再会となった。Facebook等でその後のご活躍は存じ上げていたが、互いの知見をあたため合うことができ嬉しい収穫だった。