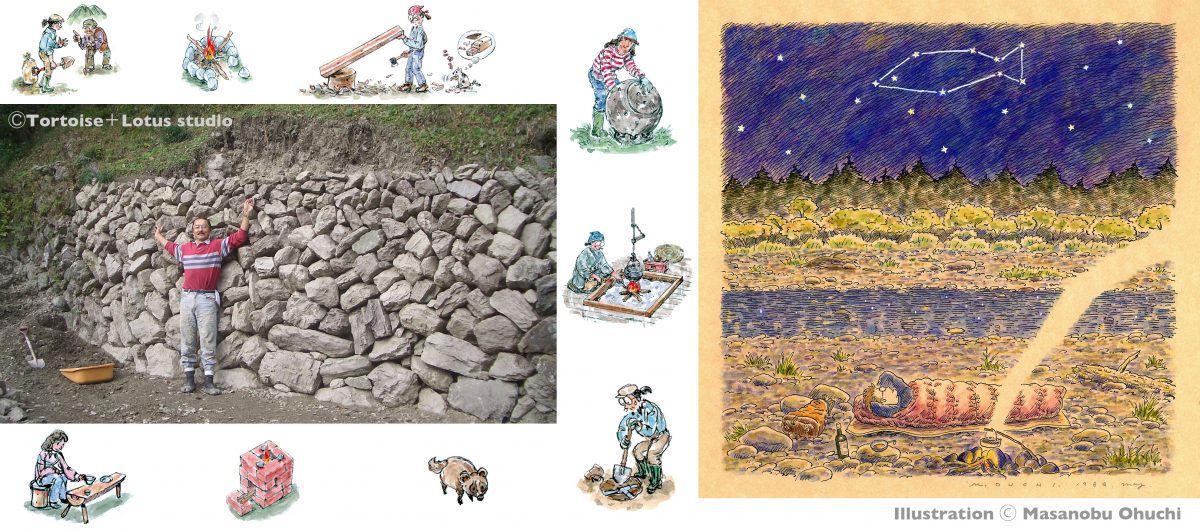この忙しいというのに相変わらず悠長に、削りたての鰹節で出汁をとった味噌汁に羽釜で薪で焚いたご飯を食べている。ご飯が旨いのはいつものことだが、取材旅行の最中に四国で買った漆器のお椀で飲む味噌汁がことのほか旨い。
これまでアトリエでは貰い物の中古椀を使っていた。それはケヤキの曲げ椀なのだが塗りがはげて吸う部分の木肌が出ていた。飲むときに口にザラっと当たって不快な感じがしていたものだ。それが、新品の塗り椀に変えたことで、汁の味が鮮やかに解るようになった。まあ、予想はしていたが感心したものである。

敷地にミョウガが出るので、味噌汁には連日これを浮かして飲んでいる。直前に切ったものを吸い口として使うのだ。穂紫蘇を浮かしてもすてきである。カボチャとジャガイモをぽくぽくに煮て、出汁の効いた汁に味噌を溶き入れ、さっと一煮立ちさせた後で、椀によそる直前に吸い口を浮かせるのである。
「吸い口」とは、すまし汁やみそ汁などをよそってから添えるものを言い、汁もの香りを添え、味を引き立てる。ほのかな香りには、食欲を増進させる効果もある。ねぎや七味とうがらしなどはよく使われるが、春は木の芽やふきのとう、夏はみょうが、秋から冬はゆずと、旬のものを使えば、季節の演出にもなる。
考えてみれば、これは漆塗りの椀あってこその文化なのかもしれない。木の椀というだけではダメで、陶器椀でスプーンなんかで汁を飲んでいては、この吸い口の醍醐味は味わえない。箸を使う東アジア限定だし、季節の水の鮮やかさをいうなら、極東限定の「食文化の粋」と言えるのではないか。
吸い口を味わうことを先に求めるなら、漆椀が必要だし、繊細なだし汁が必要なのだ。漆は日本の森が生んだ工芸材料の筆頭といっていい。繊細な汁をうみだす上質の水に日本は恵まれている。それらは森からの産物だ。この極限まで洗練された「漆塗りの椀」と「吸い口」という食文化は森あればこそなのだ。
かつて学校給食で牛乳とパンを毎日のように否応なく食べさせられ、アルミの椀に「先割れスプーン」(←知ってますか? コレ)で今思うと背筋の寒くなるような、くたびれた汁物を食べさせられていたあの時代は何だったのだろう、と苦笑するのである。
ともあれ、もぎたてサク切りミョウガの味と香りは感動モノである。ふと見上げれば目の前に霧の流れる森が見える。僕らはそそくさと片付けに入り、展覧会の準備に再び没頭する。