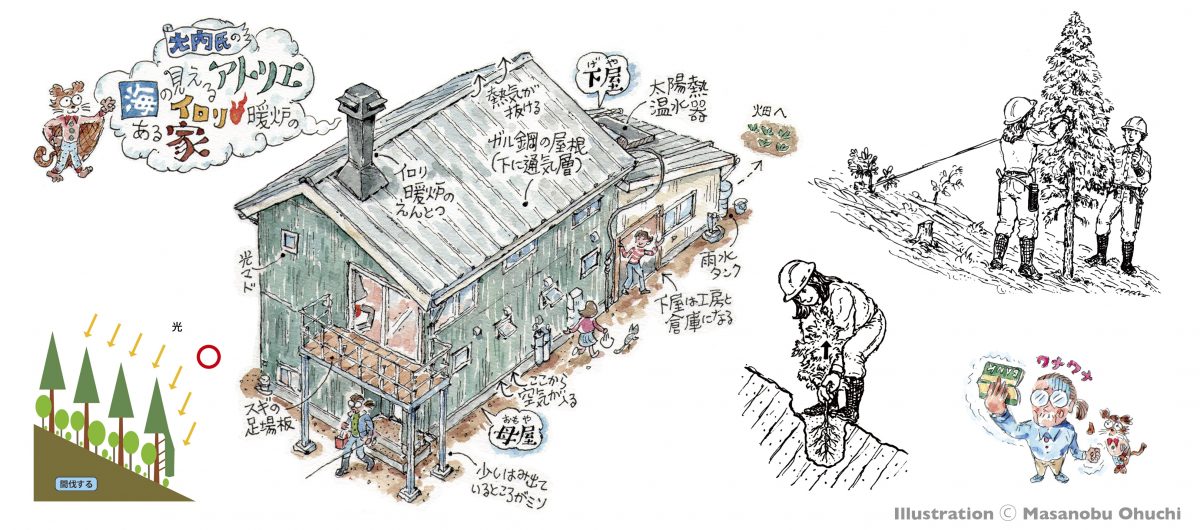退院して8日目、あまり作業はできないけれど定例活動の監督はしておきたい。そんな事情を担当のMさんに告げて、まずは前回からの敷地の変化を確認する。
見事に裸地が消えて緑が生え揃ってきた広場。まあ、そもそも草木が旺盛に成長する夏のおかげということもあるだろうが、いかにも健康そうな植物の息吹が伝わってくる。

第2回目の5月28日にはこんな感じだったのである。前年には外来種でトゲが危険なメリケントキンソウが繁茂して手で抜いて駆逐した一幕もあったらしい。

今では在来種がびっしりと地面を埋め尽くして、外来種の入る余地がない。そもそも子供の広場だからといって学校の運動場のように草全を抜く必要はないのである。「くるぶしくらいの高さで撫で刈りして『雑草の芝生』のように管理していく」という僕が言った目標に沿って、ワークショップの間の期間にも「刈りすぎないように」してもらったのである。

ヒガンバナが咲き始めた。

クリの木も枝を上げ始め、根元に草が少しずつ生え出してきた。

上と下の広場をつなく斜面の歩道は、抵抗柵が効いて草に覆われている。

ビジターセンター前の斜面。相変わらず草の伸びが穏やか。

ところが木々の根元に以前伐採した枝などが放置され腐り始めている。まだ薪になりそうなので取り出して乾かすことにした。そのほうが立木のためにもよい。

太いものは一輪車で奥の薪置き場まで運び、細いものは束ねて日に晒して乾かす。このまま今日の炊事薪に使いたい。

斜面上部のササがだいぶ衰退してきた。もうひと頑張り

この斜面の上部は、施業する前は鬱蒼としたササ原に覆われて今のようにビジターセンターは見えていないほどだった。毎年、ボランティアさんによる地際からのササ刈りが行われていたが、またササに覆われるというイタチごっこを繰り返していたのである。
それが、春からの施行でみるみるうちにササが衰退し、上部の道側にはシダ類などが一斉に繁茂するように変化してきた。

重要なのは地際からの一斉刈りをしないことである。地際から切るのは人が一人通れる程度の通路だけ。それ例外は高刈りする。それでも監督を怠ると広く刈りすぎてしまう人がいる。広く地際から刈ってしまうと乾燥が進みすぎ、素早くまたササが再生し、他の植物に入れ替わる余地がなくなる。
道の部分だけ地際から、他は高刈りすることで湿性の場所を残す。空間にメリハリをつけることで風みちができる。このような「風の草刈り」をすると、遠くから、実に気持ちのいい涼しい風が、背中に流れてくるのを感じるのである。ところが広く低く刈ってしまうと、見栄えはいいが、行き場のないぬるい風がよどみながら回るだけになってしまう。
さらに灌木の下枝を選定し、風通しを確保することで、一気に風景が爽やかになった。

昼は2つの三又囲炉裏をつくって味噌汁ときのこご飯を炊く。もう僕が手を出さなくても、炊事班の女性たちがてきぱきと炉を作り火を起こしてくれる。それでもまだ不備がある。空気の流れ、やや湿った薪の扱いなど、まればやるほど、火を燃やすということの奥深さに気づいていく。

今回もばっちり炊けた。

みんなの持ち寄りのお惣菜を囲んで。僕はもみのりを持参。

きのこは春日水神市場のエノキとブナシメジ。菌床栽培ものだが、ここの品物は美味しい。それにこんにゃくを細かく刻んだものを混ぜて炊いた(味付けは塩、醤油、みりん)。

この斜面のサクラはだいぶ弱ってきて枯れ枝が目立っていた。来春どこまで持ち直してくれえるか? 楽しみである。

午後の後半はドングリランドの下流部にある「森のようちえん」の敷地を検分に行った。ここのお母さんたちが今回のワークショップにシリーズで参加しており、その応用をこの敷地でいろいろ試しいるのである。

以前よりもだいぶ風通しがよく明るくなった。さらにわだちの処理や水切りの修正などを指導してこの日は終了。
病み上がりでちょっとしんどかったけどスタッフや参加者の皆さんに助けられました。次回はいよいよ沢と森へ‼️