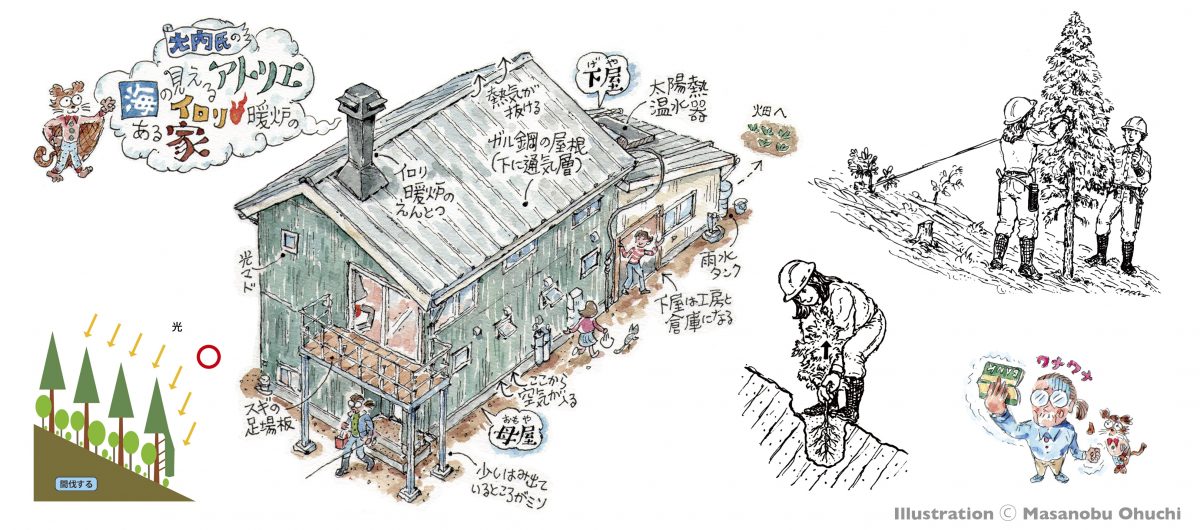午後、水路の整備から始める。2段目からの棚田には水路が不明瞭で水が入りにくくなっている。元々ホースで水を引いていたらしい。

矢野さんは効率をよくするために重機のアタッチメントをバケットに変える。

上の田んぼはさらに縦溝を増やす。

作業は2段目の田んぼに移る。刈り取られたススキなどの有機物量が多すぎるので、かき集めて外に出す(ある程度は残す)。

重機も2段目に入る。

今回は石垣側も1本だ。ただし基部から半間(約90㎝)ほど離す。掘った土は石垣側に置く。

Oさんがトラクターを運転して上がってくる。

こうしてトラクラーが入ると、水路の田んぼ側はすでに足がズッポリと抜けなくなるほど柔らかくなっている。

2段目のススキの根も抜き終えて、結作業は3段目へ。

こうして下にもトラクターが入ったが、2段目と3段目に入る水の量がイマイチ足りない。

矢野さんたちは道路の側溝をせき止め、そこにポンプを2台入れて水路に落とす作戦に出た。

3段目も大方も終えたので、カヤの木の再生に移動する。矢野さんたち重機・トラクター組みは田んぼに居残って作業。カヤの木は「大地の再生講座・中国支部」の下村京子さんの指導によって点穴を作る作業から。

各自スコップや移植ゴテを使って小さめの穴を掘る。

移植ゴテだと10㎝も掘れないが、直接根を傷めないようむしろ小さな穴でいいそうだ。

私もやってみた。最初に炭を入れ、枝を放射状に置き、スギの葉を挿しながら巻くように収め、穴の外周に軽く土をかぶせる。

根の周囲に穴を掘って炭を埋めて木を再生する手法は、元森林総研の小川真さんらがマツ枯れで実績をあげているが、矢野さんのものはより具体的かつ複雑系なのだが、誰でもできるところがよい。
こうして、各自の個性あるアートのような点穴が、カヤの木の根元にたくさんできた。

最後に草の生えていないスペース(雨の日に水たまりができてしまう部分)に有機物の残りと炭をばらまいて終了。有機物は泥漉しの役目を、炭は微生物のすみかになるだけでなく、有機ガスを吸着する効果もある。

すでに18時を回った。下の様子を見に行ってみると、2段目の田んぼに行く水を阻んでいた石垣の基部の石が取り除かれており、水が滔々と流れ込んでいた。やはり石が少し動いて(開いて)いたが、矢野さんに問うと、このような隙間には針葉樹の枝など油分の多い木のクサビを挿して締め、加えて植物の根などを隙間に入れておくといいそうだ。
一般に石垣の根石に近い石や土を動かすのは、崩す原因になるので危険視されている。しかし、放置田を再生する場合、石垣全体の空気と水の通りが良くなるという利点も大きい。これで石垣の草の根が細根化する。石垣の草は根ごときれいに抜かず、根を残して撫で刈りで管理したほうがよい。そうすることで草と石垣が一体化し、細根を通して水が出てくれる、草が味方をしてくれる。動いた石垣にクサビと植物の根・・・私にとって新しい知見だった。

今回、もう一つ発見は、直角の切土と曲面にしておくのとでは、水の入り方がまったく違うということだった。曲面のほうがドロドロになるほど土が柔らかくなっていた。空気もまた同じで、たとえば畑の畝の角は曲面にしておいたほうが空気がよく入る。ということは・・・風の草刈りで全体をカマボコ型に整えるということは、草の中にも空気が入りやすいということなのだ。

暗くなり始めたが、皆が輪になって、カヤの木の傍で感想会が続けられる。今回ほど結の力を思い知ったことはない。なにしろ1日で3段の棚田が再生してしまったのだ。「まさか今年田植えができるまでになるとは思わなかった・・・」と、Mさんらも驚いている。
人が思ったことを行動につなぐ、ゼロを1にする取り組みをする。気が現実になる。気持ちから行動を生み出す。各地域で、命がけでやれば現実が変わる。今は、現実と人の気が通わなくなってしまった。人と大地が遠のいてきた。
自然と人、人と人、気が行動になり現実になる。その力を結を通して地域や家庭の中にも日常的に取り入れていく。なんとか持続的に、「結」を通して・・・。
人間もまた「群れ」の生き物である。動物として、厳しい自然の中で生きるために、いい意味で群れる必要があるのだ。人間らしさ、群れとしての人間らしさを保ちながら。
「ここを守ってきたOさんが『生きてきてよかった』と思うような場所にしてください」(矢野)、「『大地の再生米』が作れるよう頑張ります」(Mさん)、という珠玉の言葉を残して、熊野の2日間は終了した。