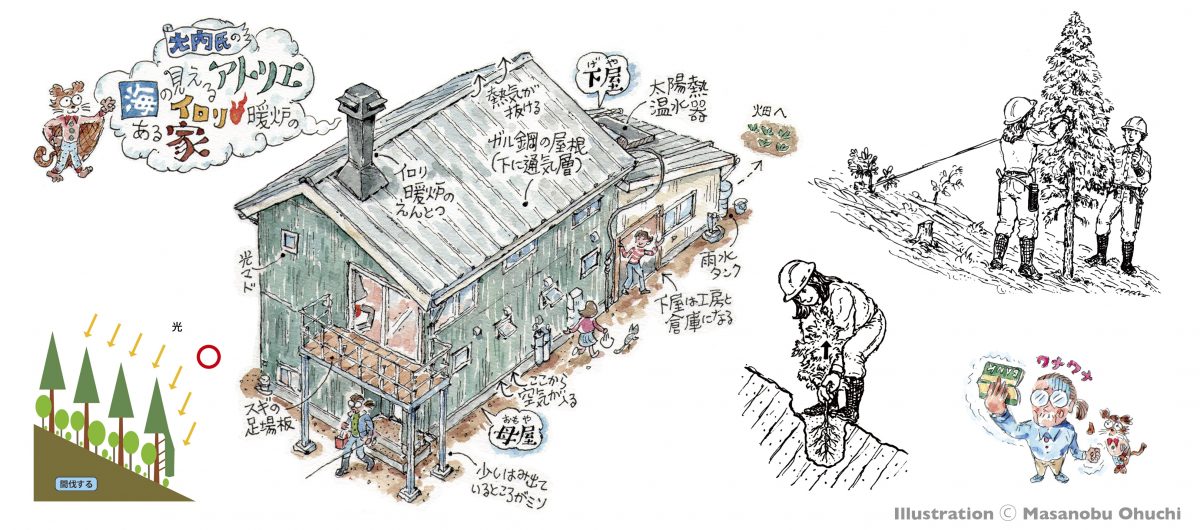このところ高松も朝は氷点下で霜が降りている。午前中、ブログ2本アップ。作業机のイラストを描く。私の木工のイラストはパース・展開図を合体させ、さらに必要な細部を入れ、その一枚で構造と作り方が直感的に理解できるように描いている。これは牧野さんの『新日本植物図鑑』の描き方・情報量に近い。
イラレやキャドは確かに便利だが、冷たくて愛がないというか、材料の取り出しや数量計算にはいいかもしれないが、かえってごちゃごちゃして形や表情が伝わってこない。
さて、午後から「背負い子」作りの続き。八ヶ岳の山小屋バイト時代、背負い子は毎日のように使ったものだ。また群馬の山暮らし時代もそうだった。背負い子はたいていスギかヒノキで手作りされていて、2本の縦棒は梯子のように平行ではなくて、内側に微妙に傾いている。そのほうが背負って安定するし、使いやすいのだ。
その背負い子のほぞのころび(傾き)をどのようにスミ付けしたらいいか悩んでいた。角度が30度とか60度のような解りやすいものなら分度器を使えばいいが、図面を描いてみると高さ800mmの中に3本の貫(ぬき)を入れとして一番上は芯芯で250mm幅、一番下は300mm、本の高さは600mmだから、三角関数で計算すると1.79度だ。これでは理論上算出できても定規からスミ付けするのは困難だ。

そこで実物大の紙型を作ることにした。それから材に転写すれば間違いない。

描いてみるとほんとうに微妙な傾きなのだ。

材を合わせて、鉛筆でアタリをつける。

線が引けたらもう片方に転写。ズレないように養生テープで止めてから。

貫の部分も。芯同士を合わせてから上下のズレをアタる。

スミ付けができたらその線に沿って組んでみる。そうして真ん中の貫にアタリを取る。

次いでほぞのスミ付け。

この場合、け引きは使わない。側面に鉋で薄くしたときの誤差が出ているのでセンターをとってから振り分ける。3分(9mm)ほぞだが、10mmでスミ付けしておく。

ノコ引き定規で切れ目を入れる。

切り過ぎないように。

あとはノミで割り・削り。ほんとうは縦引きノコで切ったほうが正確で早い。が、しっかりと材を止める治具がないとノコがブレてしまう。私は万力を持っていないのでノミでいく。

3本できた。

しかし、スギはつくづくすごい素材だと思う。軽く、サクサクと削りやすいのに、ほぞ組みに耐えるほどの強度がある。また、昔のスギの建具などはいったいどんな道具を使ったのか?と信じがたいほど加工が細かい。おまけに木目が強く浮き出て美しいときている。匂いもいい。そして使い込むほど艶が出て渋くなる(だからスギ材に塗装を施したいと思わない)。洋材でこんな素材はまず見当たらない。
スギの強度、その秘密の一つは冬目にある。木目の濃い色の部分である。全体は柔らかいのに、ここだけは非常に硬い。成長が鈍る冬の木目なのだが、この部分が軽くて柔らかなスギ材に仕込まれた、背骨・リブになっているのだ。つまり、スギという木は、日本の豊かな四季が、夏と冬との激しい落差が、その特徴を生み出している。

私はかつてスギの間伐材からクサビとヨキで板を取り出し、それに蟻ほぞを入れて鍋ぶたを作ったことがあるのだが、ほんとうにきれいに出来上がって自分でも驚いたものだ。当時、世間でスギの間伐材で作るものといえば、ベンチだとか植木鉢だとか、おおぶりの雑多なものばかりに焦点が当てられていたからである。
ほぞ穴を一つだけ空けてみた。インパクトドライバーに6mm径のドリルを装填して上下から穴を空け、ノミで削り出す。

どちらも10mmでつくっているので最初は入らない。ほぞを削りながらキツキツに入るまで調整するとちょうど3分(9mm)くらいになる。

なんとか目処がついたので今日はここまで。