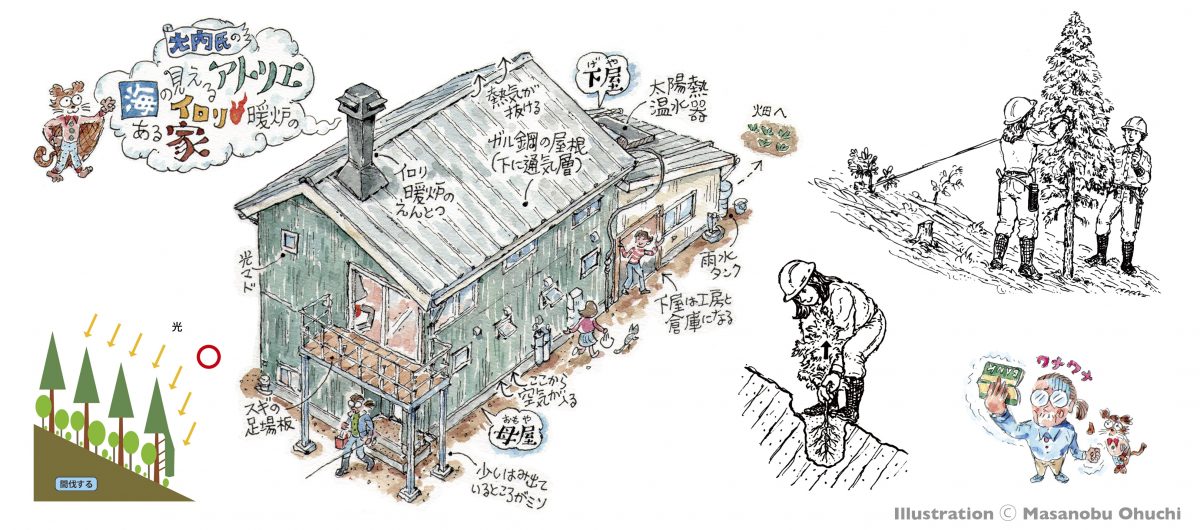朝から畑。この季節は苗や種の水やりとか除草に忙しい。除草といえば、春先は「この植物を残してやろう」とか悠長にかまえているのだが、この季節になるとトンでもないことになってしまう。水路に残したクレソンはバケモののように増殖して水路をふさぎ始めるし、猪ちゃんにワサビを荒らされてがっかりしていた湿地は、イタドリなどが大きな葉っぱをわさわさとつけてジャングルのようになっている。旅でアトリエを3日も空けようものなら、草木の成長でちがう景色になっている。



これほどに日本の山間部の植物の成長は旺盛だ。昨晩、南米パタゴニアの自然保護に打ち出すイボン・シュイナード(アウトドアメーカー「パタゴニア」の創業者)のニュース・ドキュメントを見たが、かの地はかつて森林だったところを開拓民が伐採、放牧を経て、荒涼とした砂漠に近い原野がみえている。表土が流され、自然の力では容易に森林化しないのだ。日本の山間部ではこんなことはあり得ない。鉱毒などで土壌が痛んでいるか、常に崩壊するようなガレ場か、樹冠が密閉した荒廃林(嗚呼!)以外は。それだけ多くの条件に恵まれているのだ。
植物について最近気付いたことがある。ある種の雑草がはびこるということは、その地に適したものだから生育するのだけれど、その種はそこにずっと繰り返されるわけではない。昨年、上の畑はトマトもナスもキャベツも育ちが悪かったが、今そこにはクローバーやカラスノエンドウなどの地力を肥やしてくれる植物がたくさん生えてきている。また下の畑の下部にはフキとともにスギナが多い。スギナは酸性土壌に生えるが、自らはカルシウムをつくって土壌を中性にしていくのだそうだ。一方、シラカシ大樹の下のミニ畑の雑草はハコベが多い。これはアルカリ土壌を好む草だ。
以前のブログには「不要な帰化植物を取り去り、除草をコントロールしていけば、ひとつの林縁+野草+栽培植物という有用さと美しさに満ちた新たな系ができていくのではなかろうか」と書いた。が、ひょっとしたら、帰化植物にも役割があるのではないか? 帰化植物は荒れ地などの「植生が人為的に撹乱された場所」に生える。そして、ずっとそこに生え続けることはないだろう。
自然は常に中庸なもの、安定したもの、美しいもの、荘厳なもの、に向かって生成発展していくようになっている。これが地球という星、いや全宇宙の法則だ。進化とはそういうものだ。目の前で繰り広げられる小さな変化は、進化のひな形であり相似形になっているのではないか。
トキやコウノトリやツル類が江戸時代の昔のようにたくさんいたら、こんなにブラックバスがはびこっただろうか? 草を刈りながらそんなことを考えた。
コメント